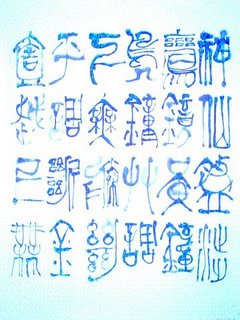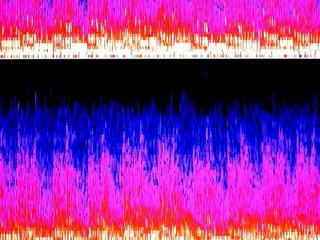photo:shovel
photo:shovel
前項ブログで紹介した村上隆の、「作品の価値とは実体のない虚構から生まれるものなのです」、は私にとって頂門の一針だった。
それはなぜか、真実だからである。激戦区アメリカアートシーンで認められた人間の言葉ゆえ、あらゆる仮面装飾を取り払った後の言葉である。
5年間の成長率40万%という桁違いの恐竜スーパーサウルス並みのベンチャー企業「Google」と、それは重なった。
グーグルは博士号候補による論文アルゴリズムを携えて発足したアメリカの若手ベンチャー企業である(アルゴリズムプログラムシステムのデジタル構成だが端末に現れた裾野ではアナログ的コンテンツを売るデジタル企業)。その点を多方面から比較してインターネットデジタル社会とは、どう云うことを意味するのか。
旧来の権威・プロフェッショナルという恐竜の頭部分に相当する寡占的支配の常識的概念、というより人間世界で約2000年間に培われた自然科学的意識から簡単に脱却できない実像世界観との葛藤ジレンマが表出している、とでも表現すべきか。そしてインターネットにおける不特定多数を狙った玉石混交の中の石の部分、その、にわかに宝になり得るというデジタルコンテンツをネットを介して分け与えたことによって新たに注目され始めた。その方法論がいまだに確立していない状況でサイトコンテンツ提供者ポータル他、ネットメディア提供者は自身の内部においてはデジタルテクノロジーを駆使してサービスを提供するが、出された媒体は人間感覚に訴えるアナログ世界である。
ネット世界が革命を起こす、とはそのメディア提供者が声を高らかに叫ぶことではなく、ロングテールの玉石混交「石」であるセクションが宝になった時であり、圧倒的多数が怒涛の如く世界を覆いつくしたときに始めて革命的といえるのではないか。そして、私とアナタはデジタルテクノロジーの道具である楽器演奏、イラスト、映像等を使って個性感情を表現する。その内容がどうであれ、良い悪いと判断するのは権威でもなくプロでもなくサイト提供者でもなく私とアナタである。
そんなことを村上隆語録「実態の無い虚構である」と私に教えてくれたのである。
プロの歌手が一人で年間1億円稼ぐ金を、1000万人の素人歌手が一人10円稼ぐこと、それがネット世界である。当然その10円で生活は出来ない。生活費は従来の企業で働いて稼ぎ出し余暇を使ってパソコン発信する。それがきわめて現実的であるし不特定多数億単位を取り込むことを前提としたネット社会では単純な計算式である。その1000万人の磨けば宝になるであろう私やアナタにサイト提供者は何が出来るか。広告収入が企業生命の母体であるなら、それを支えているのが私とアナタたちである。その個人に「サァ、宝になって下さい」とステージを用意しデジタルソースを提供して1000万色のカラーを創出することが出来るのがサイト提供者である。個人の表現力を引き出させる優れたソフトを提供することによって、そのサイトのユーザー獲得にも繋がるであろうし又、広告挿入によって購買力アップも期待できる。なにしろネット社会は数の論理であり、もっとも得意とするジャンルなのである。
確率ゼロに近い1億円宝くじと、確率50%の10000円宝くじの、どちらを選ぶか、それは主要サイト提供者も「私とアナタ」もまったく同じ線上に立っている。