
 photo:8月12日の夕焼け8月12日は千葉県に雷雨注意報が出て断続的に雷と雨が激しく停電もあった。その夕方の空は絵に描いたような景色が展開してその時思わず撮った写真。
photo:8月12日の夕焼け8月12日は千葉県に雷雨注意報が出て断続的に雷と雨が激しく停電もあった。その夕方の空は絵に描いたような景色が展開してその時思わず撮った写真。
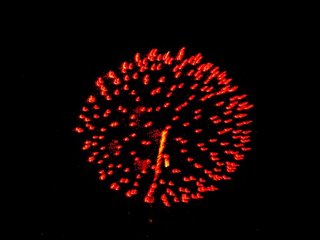
 photo:夜空の花火8月5日、私の住む町の海岸で夜、花火が打ち上げられた。家の二階から撮った写真は2キロ先の花火のため鮮明画像とはいかない。それでも夏の風物詩として雰囲気は出ているようだ。あちらこちらで盆踊りも開催され、13日より盆に入る。盆が過ぎると残暑厳しく暑い日が続くが、日照時間は確実に短くなっている。私の新パソコンもようやく起動し始めた。まだまだ入力データの整理をしていないが「温故知新」ではないが、旧きを捨て新しきを開拓する必要が沢山ある。旧パソコンのアプリケーションソフトと新パソコンのソフトに互換性がなく作ったデータも新では使えない。「春華秋実」、春の花と秋の実いずれも両立することが大切だと故事は教えるが、咲いた花から簡単には果実は実らないものと、軽いため息が漏れる。
photo:夜空の花火8月5日、私の住む町の海岸で夜、花火が打ち上げられた。家の二階から撮った写真は2キロ先の花火のため鮮明画像とはいかない。それでも夏の風物詩として雰囲気は出ているようだ。あちらこちらで盆踊りも開催され、13日より盆に入る。盆が過ぎると残暑厳しく暑い日が続くが、日照時間は確実に短くなっている。私の新パソコンもようやく起動し始めた。まだまだ入力データの整理をしていないが「温故知新」ではないが、旧きを捨て新しきを開拓する必要が沢山ある。旧パソコンのアプリケーションソフトと新パソコンのソフトに互換性がなく作ったデータも新では使えない。「春華秋実」、春の花と秋の実いずれも両立することが大切だと故事は教えるが、咲いた花から簡単には果実は実らないものと、軽いため息が漏れる。
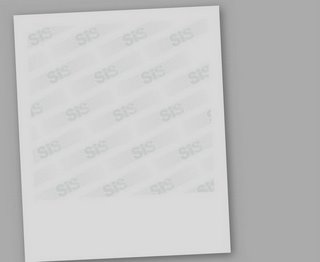
 photo:sisサンプル画像画像はパソコンに内臓されているsis社のサンプル画像を拝借した。pcリニューアルのためストックしたオリジナル画像がない。旧パソコンデータ引越しが済んでいない。外は雨、今日あたり構内LANで引越し予定…。村上隆「芸術起業論」は以前、このページで紹介した。だからといって私がその関係者だとか出版社の回し者広告屋であるとか、そうしたものには一切無関係。再び「村上隆」を取り上げたのには訳があった。私のサイトページにはアドセンス広告が張られていて記事内容をアルゴリズムのクロークが検索して適切な広告を掲示する。前回、村上隆を扱ったときクローラーは正直に村上隆の名を載せ、関連事業のサイト広告が張られた。私はかなり前から彼を知っていたが、こうした形で村上隆の名がサイトの「向こう側」に顔を覗かせるようになると、これはメジャーになった証である。彼は「LDサイト」にウェブページを展開している。今回の芸術起業論について本人がコメントを出しているので興味のある方は覗いてみるといい。ページの名は奇々怪々をもじって「カイカイキキ」(私のスイソク)と云う。彼らしいネーミングと思った。すでに著名人となった人物であるが故に堀江氏とも交流があるのだろう。前回の紹介は7月16日に読売で書籍紹介されていたものを題材にした。そして今回、8月8日の千葉日報に同様な形で芸術起業論の書籍が紹介されたのである。オヤオヤ、と訝った。私がなぜそう思ったかを説明する必要がある。それは批判でもイチャモンでも中傷でもない。むしろ新聞2紙が紹介するほど注目されている本という証明でもある。問題は、その本が手に入らないということだ。ソールドアウト状態で店頭にない。私がある書店に注文して受け取りに行くと「入荷できなくキャンセル待ち」と云われた。そんな人気のある本がキャンセルされる訳がない。そんな中で再度新聞が紹介していたので「オヤオヤ」と感じたのである。同じ村上姓で「村上龍」が作家として活躍しているが、彼のデビュー作「限りなく透明に近いブルー」が世に出回ったとき同じ現象が起きた。衝撃作として話題をさらい社会現象まで起し老いも若きも「限りなく」というフレーズを連呼した。今回の書籍は本の作家ではなくアート作家の書いた本である。いま出版界の低迷が云われている。アマゾン手法ではなく書き手の問題だ。歴史ある文学賞をとったからといって優れた内容、それが賞賛に値するものではないということだ。書き手使い捨て時代で作家本人の気質作風を選ぶのではなく「タイトル」と特異性また超日常性を長編にしてダラダラ書き綴る。読めない、読まない。その一方で「芸術起業論」が予想に反して売れ過ぎている。第2刷りを待たなければ品がない状態だ。その現象は何を物語っているのだろうか。私はその内容にあると思う。そのことを的確に著わした評論がある。千葉日報に紹介された記事で美術評論家建畠哲氏の論評を一部引用して解いてみたい。「日本のアート界の閉鎖的なモラルに甘んじてきた我々の方であって彼自身は国際的なアートシーンは歴然と欧米のスタンダードが支配しているという冷徹な現実を、そのスタンダードにおける日本のアーティストとしては例外的な勝利者の立場から、ごくまっとうに説いているだけのことなのだ」、と。これは即今の出版界にも当てはまる。ビジネスマン、マネジメントセンスがなければ芸術制作を続けることができない・欧米美術史のルールを読み解いた上で、そのルールを壊し、なおかつ再構築するに足る追加ルールを構築しなければならない・、ニューヨークやパリで劇的な反響を呼ぶことに成功する。評論家絶賛の賛辞を読んで「芸術起業論」を益々読みたくなる。しかしその本はいま店頭に並んでいない。こうした現象こそがデジタル化社会と戦うアナログ世界に絶対必要な必須条件なのである。
photo:sisサンプル画像画像はパソコンに内臓されているsis社のサンプル画像を拝借した。pcリニューアルのためストックしたオリジナル画像がない。旧パソコンデータ引越しが済んでいない。外は雨、今日あたり構内LANで引越し予定…。村上隆「芸術起業論」は以前、このページで紹介した。だからといって私がその関係者だとか出版社の回し者広告屋であるとか、そうしたものには一切無関係。再び「村上隆」を取り上げたのには訳があった。私のサイトページにはアドセンス広告が張られていて記事内容をアルゴリズムのクロークが検索して適切な広告を掲示する。前回、村上隆を扱ったときクローラーは正直に村上隆の名を載せ、関連事業のサイト広告が張られた。私はかなり前から彼を知っていたが、こうした形で村上隆の名がサイトの「向こう側」に顔を覗かせるようになると、これはメジャーになった証である。彼は「LDサイト」にウェブページを展開している。今回の芸術起業論について本人がコメントを出しているので興味のある方は覗いてみるといい。ページの名は奇々怪々をもじって「カイカイキキ」(私のスイソク)と云う。彼らしいネーミングと思った。すでに著名人となった人物であるが故に堀江氏とも交流があるのだろう。前回の紹介は7月16日に読売で書籍紹介されていたものを題材にした。そして今回、8月8日の千葉日報に同様な形で芸術起業論の書籍が紹介されたのである。オヤオヤ、と訝った。私がなぜそう思ったかを説明する必要がある。それは批判でもイチャモンでも中傷でもない。むしろ新聞2紙が紹介するほど注目されている本という証明でもある。問題は、その本が手に入らないということだ。ソールドアウト状態で店頭にない。私がある書店に注文して受け取りに行くと「入荷できなくキャンセル待ち」と云われた。そんな人気のある本がキャンセルされる訳がない。そんな中で再度新聞が紹介していたので「オヤオヤ」と感じたのである。同じ村上姓で「村上龍」が作家として活躍しているが、彼のデビュー作「限りなく透明に近いブルー」が世に出回ったとき同じ現象が起きた。衝撃作として話題をさらい社会現象まで起し老いも若きも「限りなく」というフレーズを連呼した。今回の書籍は本の作家ではなくアート作家の書いた本である。いま出版界の低迷が云われている。アマゾン手法ではなく書き手の問題だ。歴史ある文学賞をとったからといって優れた内容、それが賞賛に値するものではないということだ。書き手使い捨て時代で作家本人の気質作風を選ぶのではなく「タイトル」と特異性また超日常性を長編にしてダラダラ書き綴る。読めない、読まない。その一方で「芸術起業論」が予想に反して売れ過ぎている。第2刷りを待たなければ品がない状態だ。その現象は何を物語っているのだろうか。私はその内容にあると思う。そのことを的確に著わした評論がある。千葉日報に紹介された記事で美術評論家建畠哲氏の論評を一部引用して解いてみたい。「日本のアート界の閉鎖的なモラルに甘んじてきた我々の方であって彼自身は国際的なアートシーンは歴然と欧米のスタンダードが支配しているという冷徹な現実を、そのスタンダードにおける日本のアーティストとしては例外的な勝利者の立場から、ごくまっとうに説いているだけのことなのだ」、と。これは即今の出版界にも当てはまる。ビジネスマン、マネジメントセンスがなければ芸術制作を続けることができない・欧米美術史のルールを読み解いた上で、そのルールを壊し、なおかつ再構築するに足る追加ルールを構築しなければならない・、ニューヨークやパリで劇的な反響を呼ぶことに成功する。評論家絶賛の賛辞を読んで「芸術起業論」を益々読みたくなる。しかしその本はいま店頭に並んでいない。こうした現象こそがデジタル化社会と戦うアナログ世界に絶対必要な必須条件なのである。
新しいパソコンをセットアップして4日が経過した。今回、ディスプレートをセパレートしたので、その調整に時間がかかった。まだデータの引越し転送が済んでいない。構内ネットワークLAN で転送すると時間が省けるとマニュアルにあったので検討しているが、これも始めてのことで勝手が判らない。取り敢えずクロスケーブルは用意したが、パソコン新旧転送の設定がマニュアルを読んだだけでは理解できない。これも試行錯誤してやってみるしかない。いまのところ、インターネットから引き出した情報でパソコン操作閲覧しているが、新しい現在のパソコンには過去のデータは殆ど無い状態で必要最小限のデータだけを移行して書き加えている。このブログも、そんな情況で書き込んでいる。自分で管理しているページのデータはサイトサーバーに記録されている、ということを考えてみると、これはネット通信の最大の利点だと感心した。その全部がいいことばかりではなく、不必要な見たくも無い情報が相変わらず配信され削除する手間も大変だ。個人データが相手のサーバーに保管されているということは、サイト側として「よからぬ」情報をチェックし制限することもしばしばで、プライバシーが完全に保護されているとは云い難いが世界の安全を考える上ではやむ得ない。だったら、ついでに「低俗スパム」撃退ソフト無料配布、をしてくれたらいいだろう、と思うが大手バンクの資金がノンバンクに回り、自己破産者を生み出すシステムに、それは近い。世の中、つねに物事は表裏一体で善悪が紙一重で成り立つ。邪悪にならぬよう努めたいと思う。
8月4日午後6時25分に宅急便でパソコンディスプレーが配送されてきた。本体は既に購入してあり、ディスプレーを待つばかりであった。これからセッテング開始。長い期間のイライラをこれで解消できる。
8月1日、銚子の銚港神社で祭があった。雅楽演奏の依頼で祭の式典に欠かせない雅楽の管弦と朝日舞を奉納してきた帰り道、なにげなく寄った蓮沼の五所神社に、その絵はあった。
タイトルも謂われも作者も知れぬ、その絵は推定でも300年は経っているであろうと思われるにもかかわらず、まったく鮮度を失うことなく神社の天井に何気なく飾ってあった。明らかに神話世界を描いた物語で、真ん中の女は天照大神である。配下にはホンダワケノミコト、アメノコヤネノミコトなどの主要神を配して天空世界の神々を描いている。これほどリアルに描かれた神話絵画をこれまで観たことがなかった。まして今日まで鮮明な色彩をとどめ、また作者の筆遣いまでが克明に残っている。その筆のタッチは江戸時代前期の傑出した絵師を輩出した時代の痕跡が色濃く現れている。これは歴史的名画と直感した。そのはずで、この五所神社は昭和28年、千葉県重要文化財に指定されていた。
場所 「五所神社」 千葉県山武郡蓮沼村殿台鎮座 宮司 朝日典男
私のパソコン不調が2ヶ月も続き、その間あらゆるサポートとパソコン診断もしてもらったが回復しないまま今日に至っている。このブログを書くにも、あちらこちら経由しながら接続している状態だ。これではストレスが溜まるばかりで、まして回復見込みがないとなれば 新調するしかない。しがない極普通の生活者にとって懐に余裕があるわけではないが、買うしかない、と決断した。そして機種選定を始めた。パソコンデータの内容を表示する画面ディスプレー機能でグラフィックアクセラレータというのがある。今回初めて知ったパソコン内のシークレット部分だ。一般的には知ることの無いパソコン内ネットワークの回路で「そんなものが存在してたんだ」、という思いと、パソコン配線の複雑さを思い知らされた。大昔、回線セットするのにコンピュータはもともと人間が手でジャック挿入していたテレビ放映を思い出した。それがいま極小廉価のパーソナルになったのだから当然複雑回路になる。それで画面表示のアクセラレータに関してグーグル検索で情報を集めた。さすがにパソコンインターネットの凄さにも感心してしまう。画面サイズがアカデミー(何処のアカデミーか?)によって決められている。映画スクリーンのサイズが基本にあるようでスタンダードサイズが1:1.37で、テレビ画面がそれに倣っている。同様な基準で音楽記録のCD、MDの時間長さがあって、MDのサイズが何故74分というハンパな時間であるか、という設定は長時間クラシック一曲を入力するのに相当の時間として決め、MDもそれに併せてある、という話が或る本に書いてあった。ビスタ・サイズ1:1.66はvistavisionと云い、パラマウント映画が開発したvistavisionカメラを用い、それを一次二次加工してポジフィルムに焼付けするという手の込んだ操作で映画時代を作った。サイズは二通りあってヨーロッパビスタとアメリカビスタがある。日本映画はアメリカビスタである。パソコン画面はテレビと同サイズ仕様に出来ている。表示の目安としてGAその頭にv、sv、 x、 sx、 uxなどが表示され、それによってサイズが表される。標準サイズ、17型XGA1024×768ドットということになる。アクセラレータについて他のサイトを覗いてみるとマニアの方が投稿していた記事を読んでみると「マザーボートに付いてない機能を補う。拡張カードの選び方について」とマニアックな文が載っていた。それは私にとっての不可侵領域で、どうせ私が読んでもまったく理解出来ない。
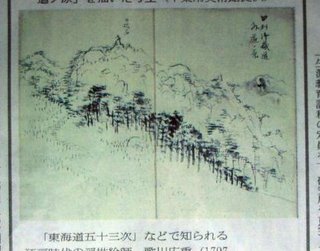
 photo:歌川広重 甲州御獄道 千葉市美術館提供・千葉日報 広重の写生帳がアメリカで80年ぶりに発見されたと千葉日報で7月27日報道されている。 千葉市美術館で9月に初公開、という案内で日本絵画研究者、そしてマニアにとっては垂涎の企画となる。
photo:歌川広重 甲州御獄道 千葉市美術館提供・千葉日報 広重の写生帳がアメリカで80年ぶりに発見されたと千葉日報で7月27日報道されている。 千葉市美術館で9月に初公開、という案内で日本絵画研究者、そしてマニアにとっては垂涎の企画となる。
江戸後期の浮世絵師本名「安藤」は歌川豊広に師事し、その師匠を超えて後世に名を残した浮世絵師である。
広重(1797-1858)の作風は江戸時代を代表する作家として知らないものはいないが、その功績はむしろ海外で評価され、印象派ゴッホに多大な影響を与えた、という逸話は余りにも有名な話しである。広重作による「名所江戸百景」が2002年ロンドンのオークションで1億円で落札されている。
日本の現代美術アートティスト村上隆の作品が同じく1億円の値がついて話題となったが、絵画嗜好のジャンル別からすれば、まったく別世界であるが金銭換算だけに限定すれば欲しいと思ったクライアントの欲求事情であり、主観的判断に1億円という値段を付けるのに誰も文句はつけられない。
江戸時代の絵師には優れたアーティストが沢山いるが、絵描きの基本である写生を誰よりも多く描いた作者ほど比例して知名度も高い。
私が所有している「北斎漫画」(岩崎美術社)には北斎のスケッチ数万点が載っており、目にしたもの全部をスケッチしたのではないかと思わせる観察力である。
いまデジタル社会でパソコンで殆どの対象が表現可能である。私もつい最近イラスト用のタブレットを買ってパソコンでイラストを描いているが、自分が描くというよりその90パーセントが機械の恩恵に載っている。とてもじゃないが、北斎のスケッチ一枚を描くに至らない。はたして、そんなものに頼っていていいのだろうか、これがオリジナル作品なのだろうか、という疑心暗鬼はいつも抱いているが、それが時代なのだという理屈をつけて納得させている。これから後、百年経過して私の絵があるところから発見されて、デジタル絵画の名作(そんなことが起こるわけはない)発見ということにでもなったら、その時代背景のインフラを分析するだろうか。広重、北斎の時代の生活習慣を我々はまったく知らない。
アフガニスタン中部バーミヤンでペルシャ神話の霊獣「シームルグ」と推定される絵柄を確認したと、文化財研究所より25日に発表された。
霊獣絵柄が発見されたのはアフガン旧政権タリバンが破壊した東西大仏立像跡の間にある石窟内だった。
天井の一部を区切る、縦約6センチ、横約45センチの梁の中央部に描かれてあった。鳥のような鋭いくちばしに獅子のような胴体、翼があり、牛と向き合っている図のようだ。
新聞にはその白黒写真が載っているが肉眼では識別不能だ。説明によると、
中央のペルシャ神話の霊獣「シームルグ」、その右側にはガンダーラ風の唐草模様、左側には牛が描かれてると説明している。
重要なペルシャ神話の霊獣シームルグが読み取れないのが残念だが、唐草模様はシルクロードより伝わる古来より普遍的な図柄であり、また牛は地中海
沿岸に広がる古代文明の神格化された象徴的シンボルとして、ギリシア神話にも登場する。そのことでも判るように、小アジアよりシルクロード経由で広範囲に情報が伝播されたことが判る。
東西文明融合の証として、霊獣シームルグは貴重な文化遺産である。

 photo:1200年祭logoマーク
photo:1200年祭logoマーク
仮想商店街、とはネット上でのバーチャル商取引を云うが、カソウショウテン街と表記されると月の上で売買取引をしているようで落ち着かない。
ポータルサイト、アマゾンが月の上で商売を始める、と新聞トップ見出しで紹介された。今更トップにするほどのことでもないと思うが。
簡単に云えば、すでに楽天、ヤフーがやっていた商圏に殴り込みをかけるという単純な構図である。アマゾン参入によって物品ネット取引が激化する、ということでIT産業にとっては活性化のために是非必要な競争である。中抜きネットと称されるくらいで介入業者不在のため単価が安く設定されるメリットがある。
私がいま個人で進めている仮想商店街はグーグルが提供するアドワーズであり、アドセンス広告に載せて小規模でもネット取引が可能なコンセプトとして注目した。アマゾンの展開する商売は数千億単位の商いを目的として現経済圏に流通する商品販売をターゲットとしているのは間違いない。私が提案しているのは、その正反対で「必要なものはすべてある生活」の中に、なにを求めるか、そこにナニを提供できるか、と云うテーゼである。もともと私はモノを販売する商人ではない。一介の会社員であり月々の安いサラリーで慎ましく暮らす人間だ。たまたまグーグルのアドワーズを知り、そのポリシーに賛同して乾坤一擲、というか個人の意思を反映して既存経済圏に物申す、という意味で思いついた。
その一方で問屋制度を核とした商取引に依存していた商人は死活問題である。遅かれ早かれ問屋は死滅する運命にあり、「ダイエー」がそのことを証明している。
私の住む人口1万人弱の街で、この7月15日に雑貨大型店がオープンした。ダイエー駅前戦略とは異なり、タンボ田園風景の中に忽然と現れた。それで休日ともなれば人口の半分が集まったのではないかと思われる程の盛況である。都会のデパート縮小版といった内容でお客のニーズ総てを満足させるという品揃えで無いものがない。私の住む近在の隣M市には飽和状態の大型店が乱立している。これは日本全国に展開している単なる一風景である。
当然のように旧来商店街は閑古鳥、シャッター通りが荒涼と広がる。そんな日本の現状経済界の中でアマゾンが開店するという。もはや閑古鳥の命はゼロに等しい。
そうした中で、私のマチでは古来より続く祭が9月13日に1200年祭として行われる。写真は、それに使われるロゴとも云うべき「手拭」のイメージで私がデザインした。祭りの形態とは地元の商店主がスポンサーとなって祭りに掛かる費用を負担して成立していた。それ以前では国、さらに遡って国領主の大名が費用一切を賄っていた。明治維新でその全部がご破算となり、地元の商い人が負担していたが、肝心の地元商店主が瀕死状態で祭を運営する費用賄いが不在となっている。かかる経費充当主がいなければ「祭り」は死滅する。メディアでは断片的に日本の祭を報道しているが、いずれ早いうちに日本から祭は足元から消えてなくなるだろう。
14世紀から16世紀に起こったイタリアルネサンス、そして近代の幕開け産業革命から今日のインターネット時代情報革命まで数百年経ったが、その間、総てを記録するというアナログ行為は現在でも引き継がれている。パソコンのキーボードが文字を打ち込んだとしても、手書き文字が消失したわけではない。むしろ、パソコンを使ってワザワザ手書き風文字を作り、それが異彩を放つ、というほど今は活字体に覆い尽くされている。古代メソポタミアの楔文字は食料生産リスト、またそれら取引を記録した文字であり、今の簿記の役目を果たしていた。だから人間は約3000年の間に渡って記録し続けていたことになる。パピルスの発明は記録改ざん防止のために考えられた、という説もあり古来より記録証拠を都合によって改ざんしたようだ。最近日本でも先端IT企業が帳簿改ざんで罪を負った。よく数字のマジックと表現するが実態と数字は別物で、厳密に現金勘定してみれば合わないはずのバランスシートは、何故か一円の狂いも無くピタリと合っている。決算報告書を読んで作った方も、見せられたほうも、それで納得してしまうから数字とは恐ろしい。たとえそれが1億円だろうが10億円だろうが金額が多くなるほど実態と合わないことは誰でも知っているが、パソコンで綺麗に清書された決算報告にケチをつけるものはいない。たとえそれが株主総会であっても動議発言するのは数字合わせではなく、幹部グレーゾーンの道義的問題を追及するのが一般的だ。スーパーコンピュータの計算速度が驚異的スピードでアップしている時代に、肝心の統計数字が当てにならない、という現実問題がアメリカで浮上している。そう指摘しているのが社会学未来学者のアルビン・トフラーだった。「知識は瞬時に世界中に配信できる」とはインターネットのことを云っているようだが、そのビジュアルに捉えることの出来ない生産物を測定また換算することがきわめて難しいと指摘する。直接表現すればマイクロソフトのWindowsでありGoogleの検索エンジンである。それに関する定義や、合意もなされていないと氏は苦慮する。帳簿を記録するという古典的手法はメソポタミア時代より行われているが、知識知恵を帳簿上に数字として書き込むことが出来ないという未知の時代がやってきたと、トフラー氏は杞憂してゆっくり安眠できないでいる。


photo:Desert
昭和51年(1976)2月4日、アメリカ上院で「ロッキード事件」が暴露された。アメリカで騒いでるから、こちらも動くか、当時そんな空気が漂っていた。月刊誌文芸春秋で田中金脈を追ったドキュメントを書いていたのが作家立花隆氏である。それが現役首相逮捕に追い込んだ一要因でもあったようだ。米ロッキード社が全日空機種選定に便宜をはかり日本の商社が仲介役で、その事件は起きた。その当時のニュースとしては、その深層まで図り知ることはなかったが、それから30年経過して、英国政府の機密文書より世界を舞台にしたカラクリが判明した。ロッキードのトライスターはロールスロイス社のジェットエンジンを搭載していた、それが理由だ。1972年9月、当時の英国首相ヒースと田中との首脳会談で、ヒースよりトライスター売り込みセールスを直接受けた、ことが機密文書で明らかになった。その際、成立すれば日本は英国米国二人の友人に手助けできる、と念をおされたという。また、その年代の日本国内問題として日英間の貿易不均衡が懸念され、工業製品・化学繊維対英輸出が急増し1970年を境に翌年1971年には英国対日貿易収支がマイナスに転じた年で、その後1972年の首脳会談である。その庇護すべきロールスロイス社は1971年2月に経営破たんした。ロッキード社の強引セールスは世界中の主要人物に及び、オランダ、西ドイツ、イタリア、コロンビアなど10カ国を巻き込んで一大スキャンダルへと発展した。(7月20日付 読売新聞記事抜粋)ときが経過して30年後のいまグローバルなインターネット時代。マイクロソフト社に追加制裁を突きつけたのは欧州連合EUである。市場で独占的な地位を持つ企業の独禁法違反に対し厳格に対応する姿勢を貫いたものだ。欧州の消費者や企業に不利益が生じる点で容認できない、というのがその理由である。(7月13日付 読売新聞記事抜粋)

 photo:8月12日の夕焼け
photo:8月12日の夕焼け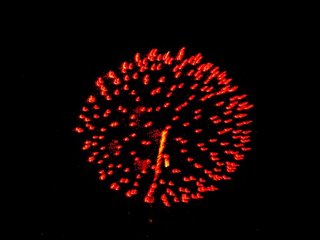
 photo:夜空の花火
photo:夜空の花火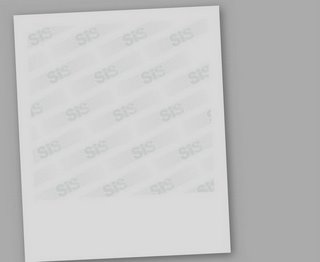
 photo:sisサンプル画像
photo:sisサンプル画像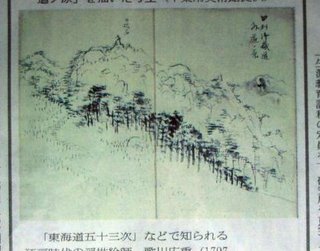
 photo:歌川広重 甲州御獄道 千葉市美術館提供・千葉日報
photo:歌川広重 甲州御獄道 千葉市美術館提供・千葉日報 
 photo:1200年祭logoマーク
photo:1200年祭logoマーク
 photo:Desert
photo:Desert