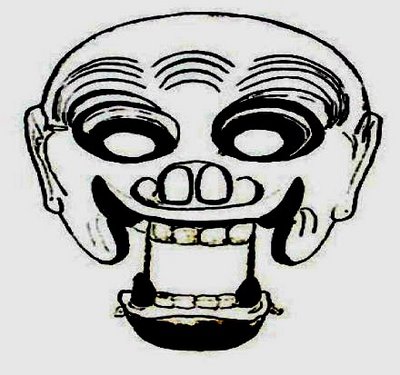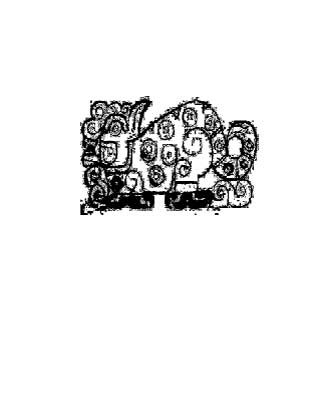ラリー・ページ、セルゲイ・ブリン
ラリー・ページ、セルゲイ・ブリンの両氏は1973年生まれの33歳。
グーグルのシステム構築に大きく貢献したジム・リースはハーバード大学生物学科卒、エール大学医学部を納め、神経外科医の肩書きをもつ。歌手ギタリストでCDも出すほど、ほとんど「天才」といって良いほどの才能を持ち合わせている。グーグル創業当時に18人目の社員としてラリー、セルゲイの両氏を支えた。
現代のPCインターネット時代を創るのに多大な役割を果たしたビル・ゲイツ氏は1955年生まれで51歳。比較の対象になるかどうか疑問だが日本のITベンチャー産業に足跡を残した(?)「堀江」氏は 33歳でグーグル創業者両氏と同年である。
何れにしても若き創業者たちによってIT産業が牽引されている。業界のそんなシーンにいるビル・ゲイツ氏は世界の富豪の一人として、まさに帝王というべきか。
ジャンルは異なるがプロゴルフ界の立役者ジャック・二クラス氏が現役時代、ゴルフ界の帝王として君臨していた。が、老齢は避けられず、その桧舞台を若手に譲って随分時間が経つ。世代交代は必然的にやってくるものである。
Googleの全貌を理解する、とは私がこのサイトでブログを書くにあたり、宣言したことだがGoogleというアメリカのIT企業を懇切丁寧に教えてくれたのが
「web進化論」(ちくま新書)の著者「梅田望夫」氏である。といっても面識があるわけでもなく、私は単なる一読者の立場でしかない。本の内容を読み進み、アナログ的には理解しているものの、実際にサイト内に潜入して「AdSenseの使い方」となると自分でマウスを触らないと判らないのがPCである。そんな意味で駑馬十駕(どばじゅうが)、一日十里の超微速だか努力すれば天才
ジム・リース氏に肉薄する、という。(殆ど無理か?)
(クーグルに関する情報すべては「web進化論」による。今後もその情報は
梅田氏の筆に依存することを、この場で言明しておく)